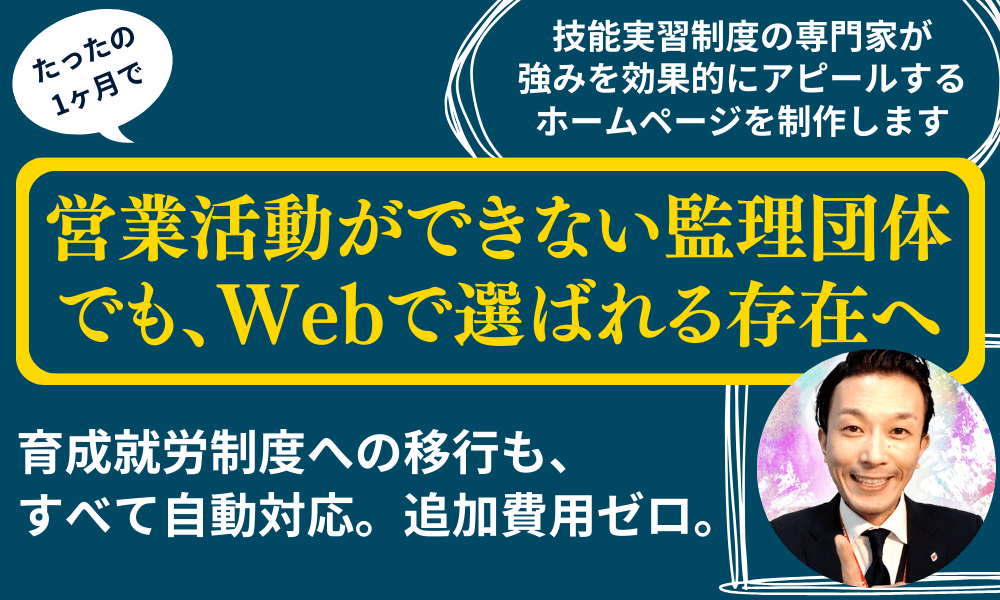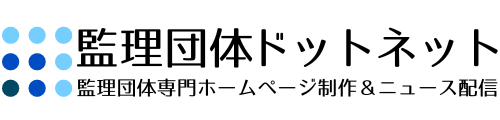出入国在留管理庁| 【「特定技能」に係る提出書類一覧表】を改定
在留資格「特定技能」
| 該当する活動 | 該当例 | 在留期間 | |
|---|---|---|---|
| 特定技能1号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が 指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要す る業務に従事する活動 | 特定産業分野での業務に従事する者 | 法務大臣が個々に指定する期間(3年を超えない範囲) |
| 特定技能2号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 3年、2年、1年又は6月 |
(注1) 各分野で従事することができる業務については、各分野の「特定の分野に係る要領別冊」を御確認ください。
(注2)「特定技能1号」については、「特定技能1号」で在留できる期間が通算で原則5年以内である必要があります。そのため、申請人の通算在留期間によっては、希望する在留期間が付与されない場合があります。通算在留期間の5年を超えて在留できる場合については、「通算在留期間」を御確認ください。
在留資格認定証明書交付申請
新しくこの在留資格で日本への入国を希望する場合の申請です。
- 在留資格認定証明書交付申請書
在留資格認定証明書交付申請書【記載例】
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿 - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 - その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を御確認いただき、必要な書類を提出してください。
※各種様式については、「特定技能関係の申請・届出様式一覧」を御確認ください。
特定技能外国人の在留資格認定証明書交付申請に係る提出書類一覧・確認表
特定技能1号
| (1)申請人に関する必要書類 | (2)所属機関に関する必要書類 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関については、 第2表の1~3に掲載されている書類は提出不要です。 | (3)分野に関する必要書類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1表(表紙を含む) | 第2表の1~3 | 第3表の1~16 | ||
| 第2表の1<過去3年間に指導勧告書の交付、又は改善命令処分を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する場合> (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 (4) 一定の条件を満たす企業等 (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (6)特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人 | 第2表の2 <法人の場合> | 第2表の3 <個人事業主の場合> | 介護 | |
| ビルクリーニング | ||||
| 工業製品製造業 | ||||
| 建設 | ||||
| 造船・舶用工業 | ||||
| 自動車整備 | ||||
| 航空 | ||||
| 宿泊 | ||||
| 自動車運送業 | ||||
| 鉄道 | ||||
| 農業 | ||||
| 漁業 | ||||
| 飲食料品製造業 | ||||
| 外食業 | ||||
| 林業 | ||||
| 木材産業 | ||||
特定技能2号
| (1)申請人に関する必要書類 | (2)所属機関に関する必要書類 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関については、 第2表の1~3に掲載されている書類は提出不要です。 | (3)分野に関する必要書類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1表(表紙を含む) | 第2表の1~3 | 第3表の1~11 | ||
| 第2表の1<過去3年間に指導勧告書の交付、又は改善命令処分を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する場合> (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 (4) 一定の条件を満たす企業等 (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (6)特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人 | 第2表の2 <法人の場合> | 第2表の3 <個人事業主の場合> | ビルクリーニング | |
| 工業製品製造業※機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分のみが特定技能2号の対象 | ||||
| 建設 | ||||
| 造船・舶用工業 | ||||
| 自動車整備 | ||||
| 航空 | ||||
| 宿泊 | ||||
| 農業 | ||||
| 漁業 | ||||
| 飲食料品製造業 | ||||
| 外食業 | ||||
申請人本人以外の方(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、
申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留資格認定証明書上の氏名と旅券(パスポート)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続において確認を行う等により、手続に時間を要する場合がありますので、提出が可能な場合には申請時に旅券(パスポート)の写しを併せて御提出ください。
在留資格変更許可申請
既にほかの在留資格を持って日本に滞在されている方が、活動内容を変更し、この在留資格に該当する活動を行おうとする場合の申請です。活動内容を変更し、他の在留資格に該当する活動を行おうとする場合は速やかに申請してください。
本来の在留資格に基づく活動を行っていない場合には、在留資格を取り消される場合があります。
- 在留資格変更許可申請書
在留資格変更許可申請書【記載例】
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿 - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 - 申請人のパスポート及び在留カード 提示
- その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を御確認いただき、必要な書類を提出してください。
※各種様式については、「特定技能関係の申請・届出様式一覧」を御確認ください。
特定技能外国人の在留資格変更許可申請に係る提出書類一覧・確認表
| (1)申請人に関する必要書類 | (2)所属機関に関する必要書類 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関については、 第2表の1~3に掲載されている書類は提出不要です。 | (3)分野に関する必要書類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1表(表紙を含む) | 第2表の1~3 | 第3表の1~16 | ||
| 第2表の1 <過去3年間に指導勧告書の交付、又は改善命令処分を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する場合> (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 (4) 一定の条件を満たす企業等 (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (6)特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人 | 第2表の2 <法人の場合> | 第2表の3 <個人事業主の場合> | 介護 | |
| ビルクリーニング | ||||
| 工業製品製造業 | ||||
| 建設 | ||||
| 造船・舶用工業 | ||||
| 自動車整備 | ||||
| 航空 | ||||
| 宿泊 | ||||
| 自動車運送業 | ||||
| 鉄道 | ||||
| 農業 | ||||
| 漁業 | ||||
| 飲食料品製造業 | ||||
| 外食業 | ||||
| 林業 | ||||
| 木材産業 | ||||
| (1)申請人に関する必要書類 | (2)所属機関に関する必要書類 ※同一年度内に特定技能外国人を既に受け入れている所属機関については、 第2表の1~3に掲載されている書類は提出不要です。 | (3)分野に関する必要書類 | ||
|---|---|---|---|---|
| 第1表(表紙を含む) | 第2表の1~3 | 第3表の1~11 | ||
| 第2表の1 <過去3年間に指導勧告書の交付、又は改善命令処分を受けていない機関であって、在留諸申請をオンライン申請、各種届出を電子届出で行い、かつ以下のいずれかに該当する場合> (1) 日本の証券取引所に上場している企業 (2) 保険業を営む相互会社 (3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業) ※ 対象はリンク先の「イノベーション促進支援措置一覧」を御確認ください。 (4) 一定の条件を満たす企業等 (5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人 (6)特定技能所属機関として3年間の継続した受入れ実績を有し、過去3年間に債務超過となっていない法人 | 第2表の2 <法人の場合> | 第2表の3 <個人事業主の場合> | ビルクリーニング | |
| 工業製品製造業※機械金属加工、電気電子機器組立て、金属表面処理の業務区分のみが特定技能2号の対象 | ||||
| 建設 | ||||
| 造船・舶用工業 | ||||
| 自動車整備 | ||||
| 航空 | ||||
| 宿泊 | ||||
| 農業 | ||||
| 漁業 | ||||
| 飲食料品製造業 | ||||
| 外食業 | ||||
申請人本人以外の方(
申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照してください。)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかを確認させていただくため、
申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本等)の提示が必要です。
在留期間更新許可申請
既にこの在留資格を持って日本に滞在されている方が、この在留資格の活動を継続して行う場合の申請です。
- 在留期間更新許可申請書
在留期間更新許可申請書【記載例】
※ 申請取次者を介して複数の申請人について同時申請する場合には次の申請人名簿が必要です。
申請人名簿 - 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
※ 申請書の写真添付欄に写真を直接印刷したものを提出いただいても差し支えありませんが、指定の規格を満たさない不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。 - 申請人のパスポート及び在留カード 提示
- その他 以下の「特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表」を御確認いただき、必要な書類を提出してください。
※各種様式については、「特定技能関係の申請・届出様式一覧」を御確認ください。
特定技能外国人の在留期間更新許可申請に係る提出書類一覧・確認表
| (1)申請人に関する必要書類 | (2)所属機関に関する必要書類 ※在留期間更新許可申請では 第2表は不要です。 | (3)分野に関する必要書類 |
|---|---|---|
| 第1表(表紙を含む) | 第3表の1~3 | |
| 全分野(農業・漁業除く) | ||
| 農業 | ||
| 漁業 |
| (1)申請人に関する必要書類 | (2)所属機関に関する必要書類 ※在留期間更新許可申請では 第2表は不要です。 | (3)分野に関する必要書類 |
|---|---|---|
| 第1表(表紙を含む) | 第3表の1~3 | |
| 全分野(農業・漁業除く) | ||
| 農業 | ||
| 漁業 |
申請人本人以外の方が申請書類を提出する場合(申請書類を提出できる方については、こちらのページを確認してください。)は、その方が申請書類を提出できるかどうかを確認するため、提出する方の身分を証する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本等)の提示が必要です。
この在留資格で在留中の方に必要な届出
※ 在留資格「特定技能」の方が所属機関を変更する場合は、在留資格変更許可申請が必要です。
- 【入国後住所を定めたとき】新規上陸後の住居地の届出
- 【住居地に変更があったとき(引っ越したとき)】住居地変更の届出
- 【在留カードの住居地以外の項目に変更があったとき】住居地以外の在留カード記載事項の変更届出
- 【所属機関に変更があったとき】所属機関に関する届出
特定技能所属機関等が行う届出
参考資料
出典:出入国在留管理庁 Webサイト
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ
「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。
その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。
その解決策として、インターネット上で24時間365日、
貴団体の強みを発信し続ける"ホームページ制作"サービスを提供しております。
たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。
そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。