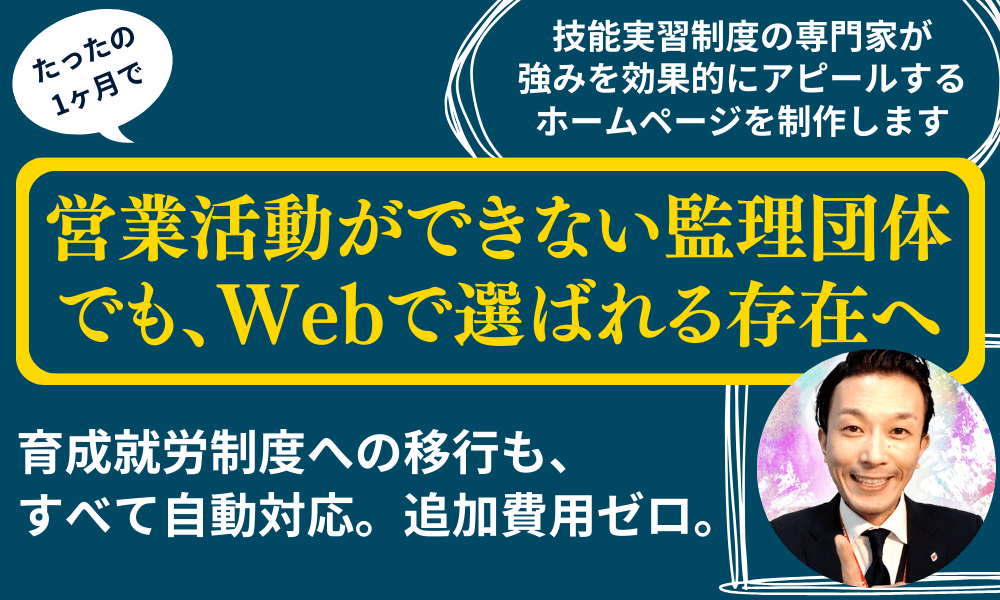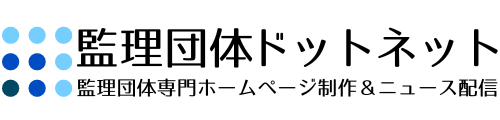厚生労働省|「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します
令和2年5月01日(金)
照会先
人材開発統括官付能力評価担当参事官室
参事官 釜石 英雄
主任職業能力検定官 中野 響
(代表電話)03(5253)1111(内線5946)
(直通電話)03(3502)6958
報道関係者 各位
「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」報告書を公表します
~「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種の技能検定についての方向性を提示~ 厚生労働省では、このほど、「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」(座長・黒澤 昌子 政策研究大学院大学 教授)の報告書を取りまとめましたので公表します。報告書では「陶磁器製造」、「ウェルポイント施工」、「印章彫刻」の3職種についての方向性を提示しました。
技能検定は、働く上で身に付けるべき、または必要とされる技能の程度を国として証明する制度で、合格した人だけが「技能士」を名乗ることができ、現在130職種を対象に実施しています。
技能検定制度の効果的・効率的運営を確保する観点から、毎年度、有識者による「技能検定職種の統廃合等に関する検討会」を開催しています。検討会では、近年の平均受検申請者数が一定の基準に満たない職種について、関係業界団体からのヒアリング、国民の皆さまからの意見募集などを行った上で、統廃合などの方向性を議論しています。
令和元年度は、検討対象に該当する3職種について検討を行い、次の結論を得ています。
■検討結果のポイント(抜粋)
| 1 陶磁器製造職種 今後、年間平均30人以上の受検申請者数を安定的に確保できる見通しを立てることが難しい状況にあると考えられ、国家検定として、これまでどおり存続させることは困難であり、職種廃止すべき。ただし、職種廃止するに当たっては、既に受検準備を行っている受検希望者に受検機会を設けるため、令和3年度の試験は実施することが適当。 2 ウェルポイント施工職種 当該職種技能士が持つスキルの内容と、それが発注者からの信頼度を高めるために有効であることを、関係業界団体の会員以外も含めた業界関係者に広く理解してもらい技能検定受検の必要性をアピールすること。さらに今後、令和2年度から起算して3年ごとの実施とすることを条件として、存続を認めることが適当。 3 印章彫刻職種 当該職種は潜在的な受検候補者数はあるものの、受検ニーズにつながっておらず、技能検定が長く実施されているにもかかわらず、受検申請者は減少している。業界全体としてその必要性が、理解共有されていないと考えられるため、廃止することが適当。一方で、関係業界団体が受検者拡大への取り組みなどを行っていることから、直ちに廃止にせず、令和3年度の受検申請者数が100人以上であった場合、かつ、関係業界団体の受検者拡大に向けた具体的な取り組みの結果を踏まえて、改めて本検討会に諮ることが適当。 |
※ 上記3職種の試験実施頻度は、以下のとおり。
陶磁器製造職種:3年ごと
ウェルポイント施工職種:隔年ごと
印章彫刻職種:3年ごと
(別添1) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書概要
(別添2) 令和元年度技能検定職種の統廃合等に関する検討会報告書
出典:厚生労働省 Webサイト
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11078.html
監理団体の理事長様へ 特別なお知らせ
「営業活動ができない」という監理団体特有の課題。
その制約の中で、どのように新規の受入企業様と出会っていくべきか。
その解決策として、インターネット上で24時間365日、
貴団体の強みを発信し続ける"ホームページ制作"サービスを提供しております。
たった1社との出会いから、紹介の輪が自然と広がっていく。
そんな仕組みづくりに興味をお持ちの理事長様は、ぜひ下の画像をクリックしてご確認ください。